菊正宗酒造 生酛づくりの世界へ・・・1day Trip レポ
今回は、灘五郷のひとつ魚崎郷にある菊正宗 酒造記念館への1day Trip のレポを行いたいと思います!

あの有名なCM「きくまさぁむねぇ~♪」の菊正宗。こんなに近くにあったのですね。灯台下暗し!灘五郷、自分の地元が全国的に有名な「酒どころ」だと知ってはいたけれど、今までなぜなのか一度も訪れたことがありませんでした。
ベーグル屋で天然酵母を扱い、小豆島に行って醤油の発酵を見学し、はたまた酒種酵母について勉強したり、クラフトビールにはまりホームブルーに手を出そうかと思案中の私。
私たちを取り巻く自然界にはほんとうに多くの菌が存在しています。そしてその菌と人間はこれまで長い間、親交を深めてきました。私たちの食とは切っても切れない関係があるのですね。今回はその中でも「日本酒」について知るために菊正宗酒造さんへ訪問してきました。きき酒もできるというからとっても楽しみ♡ワクワクのスタート!です。
アクセス:最寄り駅は阪神魚崎駅です
菊正宗酒造記念館の最寄り駅は阪神魚崎駅。JRを利用する場合は住吉駅で六甲ライナーに乗り換えて二駅目の「南魚崎駅」で下車です。南魚崎駅からは徒歩2分とアクセスは良いです。今回私は阪神電車を利用しましたので、魚崎駅下車です。

改札を出ると南出口を下って行きます。
 大きな酒造メーカーのポスターが目印です。
大きな酒造メーカーのポスターが目印です。
住吉川沿いの清流の道を南へ徒歩10分ほどで到着します。この道は遊歩道なので危なくないのですが、別のルートで目指す場合は道に信号が少ないので自動車にはくれぐれもお気をつけください!
 右側が菊正宗の工場。突き当りを左に曲がると酒造記念館の入り口が。
右側が菊正宗の工場。突き当りを左に曲がると酒造記念館の入り口が。
 酒造りに使っていた大釜がひょっこり現れます。こんなの蓋を取る時本当に熱かっただろうなぁ・・・
酒造りに使っていた大釜がひょっこり現れます。こんなの蓋を取る時本当に熱かっただろうなぁ・・・
菊正宗酒造記念館に到着
 入場は無料です。
入場は無料です。
こちらの記念館には、昭和初期まで実際に使われていた酒造用具の展示があります。職人さんたちの写真展示もあり、その仕事と生活を体感することができます。

酒蔵の夜明けの雰囲気をイメージして少し照明は落としてあります。
生酛づくりのプロセスどおりに展示されています
- 会所場(かいしょば)
作業準備や打ち合わせを行う場所。(酒造りを寒冷な時間帯に行うため、職人さんは午前2時に起きて午後6時にはもう就寝と昼夜逆転の生活を送っていたそうです!) - 洗い場
精米した白米を丁寧に洗い、表面の糠を落とす。(一日約2トンという大量のお米を3時間かけて足で踏んで洗う!!!それも真冬にっ。辛すぎ) - 釜場(かまば)
洗った米を蒸し、酒造りに適した状態にする。(大鍋にお湯をグラグラ沸かして、その上に甑を敷いて米を蒸す。その蒸米は熱々だから、職人さんは藁靴を履いて甑の中に入ってすぐに取り出したそうです。藁靴も展示されていましたが、すごく分厚いものでした。それでも熱いと思う!) - 麹室(こうじむろ)
蒸米に麹菌をふりかけ、麹をつくる。(冬でも麹菌を育てるためにこの室は高温多湿でした) - 酛場(もとば)
 麹、蒸米、水に自然の乳酸菌を取り込んで酒酵母を育てる(山卸など手間のかかる工程が特徴)。(ずらりと並んだ半切り桶を櫂ですりつぶす。大勢の職人さんが歌を歌いながら櫂を動かす姿をテレビでみたことがあります)
麹、蒸米、水に自然の乳酸菌を取り込んで酒酵母を育てる(山卸など手間のかかる工程が特徴)。(ずらりと並んだ半切り桶を櫂ですりつぶす。大勢の職人さんが歌を歌いながら櫂を動かす姿をテレビでみたことがあります) - 造蔵(つくりぐら)
生酛に米麹・蒸米・水を加え、3回に分けて仕込む(三段仕込み)。ブドウ糖を酒酵母が取り込んでアルコールを作ります。原酒となる「もろみ」ができる。 - ふなば
熟成したもろみを圧搾し、酒と酒粕に分ける。(もろみ運びと粕はがしは重労働だったといいます) - 囲場(かこいば)
しぼった酒を貯蔵し、熟成。1年間寝かせて味を深める。
続いて、樽酒マイスターファクトリーへ
菊正宗の樽酒。とてもおいしくて評判の日本酒ですが、ここにも菊正宗の伝統にこだわる姿勢が貫かれています。そのこだわりを証明するために作られた樽酒マイスターファクトリーも興味深く見学しました。
※撮影は禁止だったので、内部の写真はありません。
 記念館で集合してから歩いて樽酒マイスターファクトリーへ移動します
記念館で集合してから歩いて樽酒マイスターファクトリーへ移動します
樽酒マイスターファクトリーの見学は予約が必要です。午前10時半、午後2時、午後3時の三回です。私が訪れたのは平日でしたが、たくさんの予約のお客様がいらっしゃいました。ネット予約できるので、行く予定のある方は事前に予約してください。
係の方が説明しながら案内してくださいます。江戸時代から灘五郷で受け継がれてい来た製樽技術は「記録作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財」に指定されている貴重な技術。しかし今、その職人は減少しているといいます。
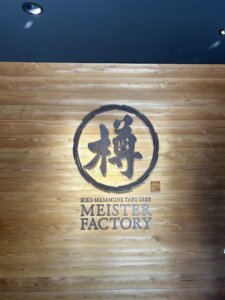
樽は樹齢百年の吉野杉。釘を一本も使わずに酒を一滴ももらさない樽を作るのですから、節のないまっすぐな杉が適しています。そのために吉野杉を育てるにも方法があるそうで、密集させて植えることで日光が遮られ葉が早く落ちる。そうすると幹はピンク色になり、優しい香りの杉に育つそうです。
そんな吉野杉で作られた樽に酒を詰めることで自然と杉の香りが移るのですね。
中では実際に職人さんが樽作りをしているところを見学することができます。機械を使っているところはほんの一部で、やはり手作業が大部分。見ていてこれは確かに重労働だと思えました。しかし後継者がいなくなってしまったら樽酒はどうなってしまうのでしょうか・・・似たようなものは機械にも作ることができるのかもしれないですが、それはきっと似ていて異なるものに違いないでしょう。
江戸時代に樽廻船に乗せられて運ばれた灘五郷の酒は江戸で大人気となります。スタッフさんの歴史の解説に、遠い江戸時代に思いをはせながらこの「日本酒」という文化が確かに地元に根付いていたことを知り、改めて感動しました。
貯蔵場を見せていただけるのですが、出来上がった樽に酒を詰めて常温で数日間置いておくと杉の香りが移るそうです。香りを均一にするために一度タンクに戻してから瓶詰めするということでした。
樽のタガ・・・説明では7本ということでしたが、数えてみると5本しかない。その理由は、「タガ」は長い竹を縦に割いて作る樽の止めバンドのようなものなのですが、近年、その材料である竹が取れなくなっているのだそう。そこで節約しているというのです。
一度使った樽は香りが抜けてしまうので杉のチップにするなどの再利用には回すけれど、樽酒作りには使えません。しかしタガに限っては材料不足のため、再利用するしかなくなっているということでした。
地球温暖化という環境の変化がいたるところに影響を与えています。「またここにも影響が・・・」といった心境になりました。
樽酒マイスターファクトリーのあとは樽酒のきき酒!

ほんのりと樽の香りがするすっきりとした辛口のお酒。冷やしてあってすごくおいしかった!

最後に盃展示館を見学しました
盃展示館では酒作りと酒器の歴史の展示があります。
冬場に酒を仕込む倉庫の一角を利用して、社員の方々が大切に集めてきた盃を展示しています。
 ここが倉庫。左側に入り口があります。
ここが倉庫。左側に入り口があります。

盃だけでなく、酒をそそぐ酒器の類もあり、その形態が時代によって変化していく様を知ることができるのが面白いです。絵巻物などの時代時代の絵を通じて、市井の人々の酒とのかかわりを知ることができます。

また、全国各地の盃の展示もあり、その土地土地の粘土の違いにより様々な個性豊かな焼き物文化が発展していくのを見るのも面白い。
とても美しい盃を見ることができるので、器好きの方は楽しいと思います。
盃展示館のあとにももう一度きき酒タイム!
このきき酒は「器が違うと同じ酒でも違う味に感じる」がテーマ。深い盃と口が広く開いた盃の二種類の盃でお酒をいただけます。

確かに深い方の盃はお酒が喉の奥までダイレクトに進んでくるのでどちらかと言えばシャープな飲み口。口の広い方は口のそばまで持ってくると香りがふわりと広がり、優しい飲み口で味も濃く感じました。スタッフの方も、「盃によってこれだけ味がかわるのだから、いろいろな盃でお酒を試してみるという楽しみも知ってほしい」とおっしゃっておられました。
確かに、これは目からうろこの体験でした。
無料試飲コーナーでまだまだきき酒ができます
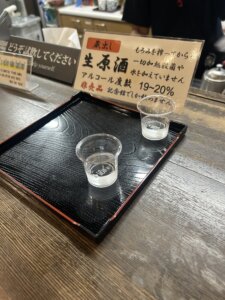 こちらは生原酒。アルコール度数が高い!
こちらは生原酒。アルコール度数が高い!
 夏にぴったりなレモン冷酒。甘くて飲みやすい。まるでジュースみたい。
夏にぴったりなレモン冷酒。甘くて飲みやすい。まるでジュースみたい。
その他、売店で販売されているお酒で気になるものがありましたら、有料で試飲できるので、試してみて購入できるのが嬉しいですね!

菊正宗酒造 生酛づくりの世界へ・・・1day Trip レポ まとめ
今回は、全国的に有名な菊正宗酒造へ訪れてみました。朝の9時ごろ家を出て、お昼一時くらいで終了しました。
灘五郷・・・こんなに歴史的な酒造り文化が近くにあったんだ!と新しい発見ができて楽しかったです。
次は西宮郷へ行ってみようかな!


